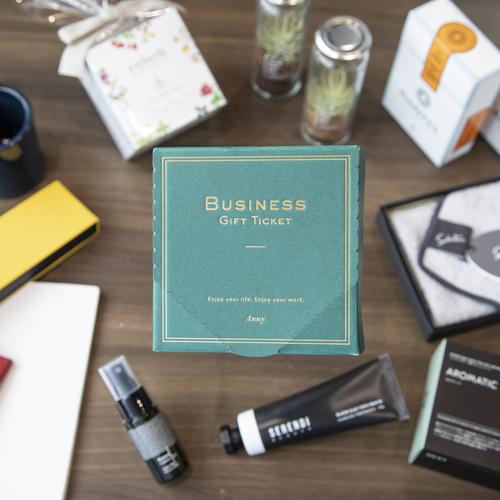結納品の正しい処分の方法3選を解説!結納金は誰が誰に渡すの?
結婚を決めたふたりが結婚式当日までに準備しなければならないことはたくさんあります。その中でも結納を行うと決めた場合は両家共に準備が必要です。結納は両家にとっての大切な儀式。また結納品には古人からの伝統や想いが詰まっています。近年では仲人も立てず簡略化してきている結納ですがやると決まればきちんと意味を知ったうえでふたりの結婚の誓いを立てましょう。そこで今回は、恋愛コーディネーターの経験を持つ筆者が結納品の正しい処分の方法などを解説します。
結納金とは?誰が誰に渡すの?

image by PIXTA / 7343914
結納をする際に必要なのが小袖料とか御帯料と表書きされた封筒に現金を包む結納金です。結納金とは誰が誰に渡すものでしょうか。また結納金の相場はどのくらいでしょうか。ここからは結納金や結納金の相場について解説していきます。
結納金とは?
結納金とは結納時に結納品の項目に含まれている現金の包みのことです。結納金はその昔、男性側が女性を嫁にもらうために支度金として渡していたのが基になっていますよ。当時は着物を買いそろえて嫁入りしたことから現代でも現金を包む封筒には小袖料や御帯料などと印字されています。
ちなみに結納金には嫁ぐための支度としての意味が強く金額は結納の習慣により西高東低と言われていますよ。また結納金についてはとくに金額や金額の上限などが決められているわけではありません。そのため金額を決める際には一般的には男性側が経済力に見合った額を決めるとされていますよ。
ちなみに結納金には嫁ぐための支度としての意味が強く金額は結納の習慣により西高東低と言われていますよ。また結納金についてはとくに金額や金額の上限などが決められているわけではありません。そのため金額を決める際には一般的には男性側が経済力に見合った額を決めるとされていますよ。
結納金の相場は?
一般的な金額としてはキリが良く100万円が多いようです。中には150万円以上という人もいますが50万、70万といった奇数や末広がりを表す80万というカップルもいますよ。その他にも金額を決めるのにはお見合い結婚と恋愛結婚なのか、両者の地域差や両者の親戚関係などによっても変わってきます。
また関東では結納返しといって結納金の半額分を何かの形で新婦側が返すことになりますよ。最初から少なめの金額を結納金として納め結納返しを省略するというのも増えています。両者の金額があまりにも違う場合にはやんわりと結納金の金額相場を話し合っておけると良いでしょう。
また関東では結納返しといって結納金の半額分を何かの形で新婦側が返すことになりますよ。最初から少なめの金額を結納金として納め結納返しを省略するというのも増えています。両者の金額があまりにも違う場合にはやんわりと結納金の金額相場を話し合っておけると良いでしょう。
結納金の渡し方とは?
結納金をはじめとしたお祝い事には新札を使うのが相場です。そのため銀行で受け取る1週間ほど前に予約を入れておくと良いでしょう。銀行によってはその日に突然行って新札をそろえられるとは限りません。また渡すときは当日受け取った側が1枚ずつ数えて確認というわけにはいかないので、帯がついている状態の新札であれば確認しやすいよう帯封はつけたまま渡すのが良いでしょう。
結納金は誰が渡すの?
結納金は名字を名乗る側の家、基本的には男性側の家から女性側の家に対して贈られるものです。現代では新郎当人が払う場合もありますしご両親が用意する場合もありますが必ずこうあるべきという決まりはありません。ひと昔前は今と比べると若い年齢で結婚することが男女ともに多かったので、結婚するまでは親の務めとして結納金もご両親が用意するというケースが多かったです。
また晩婚化や核家族化が進んでいる現代ではある程度は当人が用意する、足りない分は親に補ってもらうなどということも多くなりました。さらに男性の方が女性側へ婿入りする場合はすべての役割は逆になり、結納金の額は通常相場の2倍から3倍になる傾向があると言われていますよ。
また晩婚化や核家族化が進んでいる現代ではある程度は当人が用意する、足りない分は親に補ってもらうなどということも多くなりました。さらに男性の方が女性側へ婿入りする場合はすべての役割は逆になり、結納金の額は通常相場の2倍から3倍になる傾向があると言われていますよ。
結納金は必要なのか?
現代では仲人を立てる正式な結納を行う人たちも減り結納そのものが簡略化されてきています。そのため必ずしも結納金が必要というわけではなくなってきていますよ。結納を簡略化するようになった現代でもいまだに結納金のシステムが生き残っているのは生活力のアピールというのもあるでしょう。結納金を授受するシステムが必ずしも幸せを約束してくれるわけではありませんが形に残る儀式として結納金を準備するのも良いでしょう。
結納品の正しい処分方法5選!

image by PIXTA / 30672172
食事会だけで結納せずすませることも多い現代で結納品を用意して結納を行ったということは貴重な経験ですよ。結納品の数々もかさばりますが結婚の良い思い出の品です。ここからは結納品の処分方法について解説していきますよ。
1.食品は早めに使用する
基本的には日持ちの良いするめや昆布などの縁起物が結納品の中にありますがそれらは縁起物のため早めに食して今後の結婚を祝いましょう。そしてそれぞれの食品についている水引飾りや包みのみを飾っておきます。地域によっては結婚式のお料理に使用するところもあるので一般的には結納品をもらった家庭で食してかまいません。またお酒は結納の場でみなさんにふるまいみなさんで祝うという地域もありますがお酒も縁起物なので早めに消費して良いものです。
2.紙や木製品はリサイクルせず処分
結納金を包んでいた封書や目録用紙などの紙類と結納品をのせるための白木台は結納後一定期間飾って式が終わったのち処分しましょう。友白髪や水引なども不要であれば処分してかまいません。基本的に結納品はリサイクルしません。地方によって福分けといって兄弟や親戚の結納品を使いまわすところもありますがそうでなければ使いまわすことはしないようにしましょう。
またリサイクルなどしない結納品ですが水引は羽子板飾りにリメイクしたり女児の初節句に髪飾りとして使用したりと使い道があります。ちなみに結納の記念として水引だけ残しておくカップルも多いですよ。
またリサイクルなどしない結納品ですが水引は羽子板飾りにリメイクしたり女児の初節句に髪飾りとして使用したりと使い道があります。ちなみに結納の記念として水引だけ残しておくカップルも多いですよ。
3.捨てずに保管しておく
中には記念としてすべて取っておきたいというカップルもいるかもしれません。そういった場合は食品以外はすべて保管しておいてもかまいません。例えば紙類は処分しても良いのですが食品類は食べたらなくなってしまうので目録は大切にとっておくというカップルもいます。また結納の時に使用したお盆や木箱なども捨ててもかまわないものですが新居のインテリアとして飾るというカップルもいますよ。
4.結納品を処分するときはお寺や神社へ
紙類や木製品は燃えるごみとして市町村の条例に沿って捨ててしまっても良いものですが、日にちが経って飾っておいた水引やお盆などを処分しようという場合には神社やお寺に処分してもらうという方法が一般的です。お守りや破魔矢などの処分方法と同じ感覚ですよ。またご縁あって結ばれたふたりのための結納品なので処分するときには感謝の意を込めて処分するようにしましょう。
中にはご縁の甲斐なく離婚するカップルもいますが離婚する場合は結納品の中で日常的に使えるお盆や飾り物があったとしてもすべて処分するのが一般的です。前のご縁を引きずってしまうという意味からもすべて処分しますよ。
中にはご縁の甲斐なく離婚するカップルもいますが離婚する場合は結納品の中で日常的に使えるお盆や飾り物があったとしてもすべて処分するのが一般的です。前のご縁を引きずってしまうという意味からもすべて処分しますよ。
5.結納品の処分には地域差もある
結納が盛んな西日本エリアだと末広と呼ばれる白い扇子と高砂人形がケースに入って飾られていたり友白髪を新居の柱に結んだりといった風習があります。結納後に結納品の処分について両家のご両親に意見を聞いておけば間違いないでしょう。また新居に余計なものを持ち込みたくないという考えの人は神社に持っていきお焚き上げしてみらいましょう。
結婚してしばらくは飾っておき頃合いをみて処分するのも1つの方法。結納品については飾っておく決まりや期間などは決められていないのでご自身のライフスタイルに合わせて考えれば良いですよ。
結婚してしばらくは飾っておき頃合いをみて処分するのも1つの方法。結納品については飾っておく決まりや期間などは決められていないのでご自身のライフスタイルに合わせて考えれば良いですよ。
親は人生の先輩として有用な助言をしてあげよう!
おめでたい席に関しては親のエゴはおさえ基本的に本人たちの考え方を重視しましょう。そのうえで人生の先輩としてのアドバイスを。例えば結納で本人同士の結びつきが重視される現代とはいえ結婚後は新しい家族や親戚とのつきあいがはじまります。その親や家族の存在を無視して結婚の基準を進めて良いものではないといったことを伝えるのは親の役目ですよ。
男性へのおすすめプレゼントなら、Anny(アニー)におまかせ!
バイヤー厳選のおしゃれなプレゼントの通販なら「Anny(アニー)」へ。ギフトBOXやメッセージカードなどギフトサービスも充実!
男性への贈り物におすすめなギフト